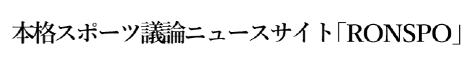判定勝利デビューした“アマ最高傑作“堤駿斗は本当に“ネクスト・モンスター”級の逸材なのか?
6ラウンドに入って堤は一気にペースダウンしていた。
3ラウンドのアマとは違う長丁場にスタミナ切れしたのか?と見ていたが、両手が使いものにならず攻撃を仕掛けることができなくなっていたのである。ジャッジの1人が79―73とつけていたが、唯一、相手につけたラウンドがこの回だった。
それでも7ラウンドは、ジャブからワンツーで主導権を渡さず、最終ラウンドのゴング寸前にワンツーから左フックを思い切り振ってワンチャンスを狙った。
「相手からも来い、来いと言われた。下がっては終われない。ラスト10秒は打ち合いにいった」
堤が見せた矜持だった。
セコンドについた父の直樹さんからは「万全な状態でリングに上がるのがプロの仕事だ」と諭された。アマ時代には当日計量に苦労して実力を発揮できない試合も少なくなかった。今回は友人の天才キックボクサー那須川天心の元フィジカルトレーナーの指導を受けて、減量と、6キロを戻すリカバリーを万全に整えた。
試合中には、その父から「遠い距離でどんどん打っていこう。前の手(左)が単調だから工夫していこう」とアドバイスを受け、渡部浩太郎トレーナーからは「練習でやったことを最後まで貫こう」とハッパをかけられた。
戦いながら、パンチが当たればどっと沸き、膠着すればシーンと静まるプロ特有の会場の雰囲気に「ファンの方は正直。そこがプロだと感じました」という。
さて、その堤の可能性についてである。
試合を組み立てた左ジャブにはスピードがあった。老練なフィリピン人のガードをこじあける角度と強弱があり、ワンツー、特に右のストレートは数種類を使い分けていた。
パンチャーは一発に頼りがちだが、堤の非凡さは、コンビネーションブローが多彩で、デビュー戦から冷静にボディを絡めて上下にも打ち分けられていた。またタイミングを見計らっての右のストレート、左のフックのカウンターも絶妙で、4ラウンドには、左フックでぐらつかせてラッシュをかけるシーンも演出した。 堤は、「ちょっと狙いが単調になって、中盤、相手を見過ぎたが、最後まで前の手のジャブはひとつの武器として当てることができた点はよかった。右のカウンターを何回か当てられた」と振り返った。
そして特筆すべきは、そのディフェンス力である。
「プロの8オンスでは、見えないパンチをもらうと倒れる。攻めるよりもしっかりと見て、パンチをもらわないこと。相手の距離ではなく自分の距離で戦うことをテーマにしていた。効いたパンチはなかったが、ガードの上からも重たかった。アマとは違うと思った」
その中でも堤の長所はステップワークにある。体の位置を変え、常に安全な距離を俊敏なステップバックで作っていた。ガードも高く強固で致命的な一撃は、もらわなかったが、入り際に不用意な左ジャブ、接近戦ではアッパーを浴び、その右目は少し腫れていた。